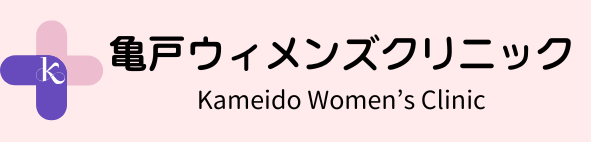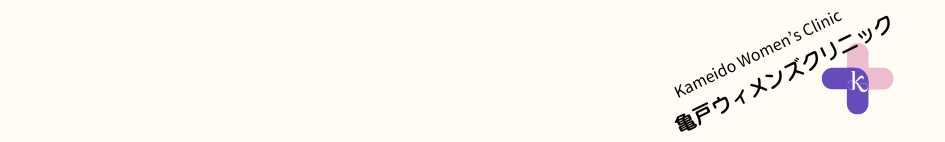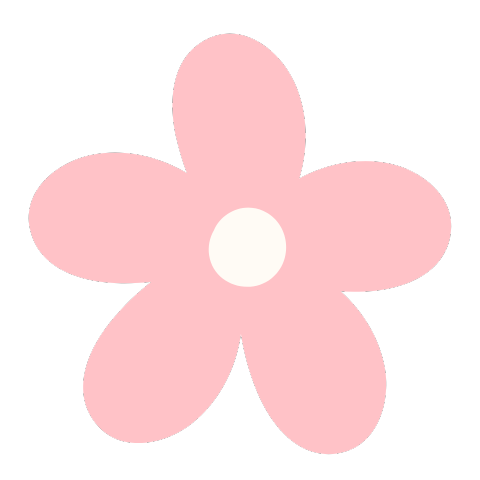あなたのお悩みは?
月経不順

症状
- 月経周期が不規則で、一般的な月経周期 (25-38日)よりも短かい、または長い。
- 月経が数ヶ月間来ない。
- 1か月に何度も月経が来る。


原因
月経不順は、ストレス、生活習慣、体重の変動などのさまざまな要因によって引き起こされます。
ストレス
精神的なストレスや生活環境の変化などが月経に影響を与えることがあります。
体重の変動
急激な体重増加や過度のダイエットなどがホルモンバランスに影響を与えます。
運動習慣
過度の運動や運動不足が月経周期に影響することがあります。
薬物の影響
抗うつ薬やホルモン剤など、一部の薬物は月経周期に影響を与えることがあります。
疾患
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)、甲状腺疾患、高プロラクチン血症などの疾患が関与していることがあります。

治療法
月経不順の治療法は多岐にわたりますが、個々の症状や原因に応じた最適な治療を行うことにより症状の改善が期待されます。
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)
多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)は、卵巣に複数の小さな嚢胞 (卵胞) が形成されることが特徴です。
-3-1-1024x819.png)

症状
月経不順、多毛、ニキビ、脂性肌、不妊、体重増加など。

診断方法
問診、血液検査、超音波検査

原因
遺伝的要因やインスリン抵抗性などが関与していると考えられていますが正確な原因は不明です。

治療法
生活習慣の改善、減量、薬物療法(ホルモン療法やインスリン感受性の改善薬)、不妊治療。
月経困難症
日常生活に支障が出る程の重い症状を月経時に認める場合を月経困難症と呼びます。

症状
身体的症状
下腹部の鈍痛や鋭い痛み、頭痛、腰痛、吐き気、など。
月経時の症状は個人によって異なり、軽度から重度までさまざまです。もし症状がひどい場合は、産婦人科医にご相談なさることをお勧めします。


原因
機能性月経困難症
明らかな疾患は認めませんが、月経に伴って痛みが生じる状態を指します。主にホルモンの変動や子宮の収縮によって引き起こされます。
器質性月経困難症
子宮や卵巣などの疾患や病変異常にによって痛みが引き起こされる状態を指します。原因として、子宮内膜症、子宮筋腫などが考えられます。

治療法
薬物療法
- 鎮痛剤:月経困難症の痛みを和らげるために使用します。
- ホルモン治療:ホルモン剤を使って月経をコントロールし、痛みの軽減を図ります。
- 子宮内避妊具(IUD):ホルモンを含んだIUDを使用することにより月経痛を軽減することができます。
生活習慣の改善
- 運動:定期的な運動(ウォーキングやヨガなど)が血行を促進し、痛みの軽減に効果があります。
- ストレス軽減:ストレスや不安が月経困難症の症状を悪化させることがあるため、リラクゼーションや瞑想や深呼吸などを取り入れることが有効です。
- 食事:バランスの取れた食事を心がけましょう。
手術療法
- 器質性月経困難症の場合、子宮筋腫や子宮内膜症などがある場合、手術によって子宮筋腫や内膜症病変を取り除く手術を考慮することがあります。
子宮内膜症
子宮内膜症は、子宮内膜が子宮以外の部位(卵巣、卵管、直腸、腹膜など)に存在する疾患です。この子宮外に存在する子宮内膜は、ホルモンの影響を受け、月経時に剥がれ落ちることにより周囲の組織が炎症を起こし癒着や強い痛みを引き起こします。
-2-1024x819.png)

症状
月経痛、過多月経、性交痛、排便痛、腰痛、不妊など。

診断方法
内診、超音波検査、MRI、腹腔鏡検査。

原因
正確な原因は不明ですが、遺伝的要因、免疫系の異常、月経血がおなかの中に逆流すること(経血逆流説)などが関与していると考えられています。

治療法
薬物療法:鎮痛薬を使用し痛みを和らげたり、ホルモン療法(ピルやプロゲスチン製剤など)で内膜の増殖を抑制します。
手術療法 : 症状が重い場合や薬物療法で効果が乏しい場合は、内膜症の組織を取り除く手術が行われることがあります。
生活習慣の改善 : ストレス軽減や適度な運動、バランスの取れた食事なども症状の改善につながることがあります。
子宮筋腫
子宮筋腫は、子宮に発生する良性の腫瘍で、がんなどの悪性の病気ではありません。子宮筋腫は非常に一般的で、30歳以上の女性の20-30%にみられると言われています。
-1024x819.png)
子宮筋腫は存在する場所によって以下の3種類に分類されます:
- 粘膜下筋腫: 子宮内膜の直下に存在し、過多月経や不妊症の原因になることがあります。
- 筋層内筋腫: 子宮の筋層内に存在し、大きいものは過多月経や流産・早産の原因となることがあります。
- 漿膜下筋腫: 子宮の外側に突出している筋腫で、大きくなるまで症状は乏しいです。

症状
無症状のことも多いですが、過多月経、貧血、月経痛、腰痛、頻尿、便秘、不妊症などの症状を呈することがあります。

診断方法
内診、超音波検査、MR検査など。

原因
女性ホルモン(特にエストロゲン)の影響で大きくなるため、閉経すれば子宮筋腫も小さくなります。

治療法
無症状の場合は治療はせず経過を観察します。症状がある場合には薬物療法や手術が考慮されます。
月経異常

症状
過多月経
月経時の出血量が多い状態を意味します。
過多月経には主に以下のような症状があります:
- 生理が長く続く(7日以上)。
- 生理の出血量が多く、1時間毎など頻繁にナプキンやタンポンを交換する必要がある。
- 大きな血液の塊が排出される。
過多月経の原因として、子宮筋腫、子宮内膜症、ホルモンバランスの乱れ、血液凝固障害などが考えられます。
過少月経
月経時の出血量が少ない状態を意味します。
過少月経には以下のような特徴が見られます:
- 月経期間が短い:月経の持続期間が短く、1〜2日程度で終わることがあります。
- 月経量が少ない:生理中にナプキンやタンポンの交換頻度が少なく、少量の出血しか見られないことがあります。
- 経血が薄い、または点状の出血である:経血の色が薄かったり、少量の血液が時々出ることがあります。
過少月経の原因としては、ホルモン異常、ストレスや体重の変化、過度な運動、甲状腺疾患、などが考えられます。


原因
月経量異常 (過多月経や過少月経) の原因はさまざまですが、主なものには以下のような要因があります。
ホルモンバランスの乱れ
エストロゲンとプロゲステロンのバランスの乱れが月経周期に影響を与えます。バランスが乱れる原因には、生活習慣(急激な体重の増減、ストレス)や年齢(思春期や更年期)などが挙げられます。
疾患
- 子宮筋腫、子宮内膜症、子宮内膜ポリープなどが出血を引き起こしたり、出血量を増加させたりすることがあります。
- 血液が正常に固まらないこと (血液凝固障害) により、出血量が多くなることがあります。
- 甲状腺ホルモンの異常が月経に影響を与えることがあります。
薬剤
避妊薬や抗うつ薬などが、ホルモンに影響を与え月経量を変化させることがあります。

治療法
ホルモンバランスを整えるために、ピルやエストロゲンとプロゲステロンを用いたホルモン治療などが行われます。生活習慣の改善(定期的な運動、ストレス管理、健康的な食事)が症状の緩和に役立つこともあります。子宮筋腫や子宮内膜ポリープが原因の場合、それらを取り除く手術が行われることもあります。
不正性器出血
月経周期以外の時期に出血がみられることを、不正性器出血といいます。原因は様々ですので、不正出血が見られた場合は早めに受診することをお勧めします。

症状
月経以外のタイミングで起こる異常な出血を指します。
✔ 期間
短時間で止まることもあれば、何日も続くこともあります。
✔ 出血量
少量のことも大量のこともあり、さまざまです。
✔ 出血の色
明るい赤色から茶色、黒色まで、出血の色はさまざまです。


原因
ホルモンバランスの乱れ
精神的なストレスや体重の急激な変化がエストロゲンやプロゲステロンの分泌に影響することがあります。
妊娠
妊娠初期の出血や流産の兆候として不正性器出血が見られることがあります。
子宮の疾患
子宮内膜症、子宮筋腫、子宮頸部病変などが不正性器出血を起こすことがあります。
性感染症
感染症により膣や子宮頸部に炎症が起き、出血を引き起こすことがあります。
ホルモン異常
ピルやホルモン治療を受けている場合、その副作用として不正性器出血が生じることがあります。また、ホルモンバランスが乱れると出血が起こることもあります。
外傷
性交渉や他の外的要因による外傷が原因となることがあります。

治療法
不正性器出血が起こる原因を明らかにすることが重要です。原因に応じて、薬物療法、生活習慣の改善、手術などの治療法を行います。
PMS(月経前症候群)

症状
精神的症状
イライラ、不安、落ち込みなどの感情の変化、睡眠障害、など。
身体的症状
腹痛、頭痛、腰痛、むくみ、乳房の痛みや張り、食欲の変化、便秘や下痢、疲労感、集中力の低下、など。

これらの症状の出現は個人によって異なり、症状の程度もさまざまです。日常生活に支障をきたす場合は、医師に相談することをお勧めします。

原因
PMSの原因は完全には解明されていませんが、以下のような要因が関与していると考えられています:
- ホルモンの変化
- 月経周期に伴うエストロゲンやプロゲステロンなどのホルモンバランスの変動
- 精神的なストレス
- 不規則な食生活、運動不足、睡眠不足などの生活習慣
- セロトニンなどの神経伝達物質のレベルが変動
- 家族にPMSの症状を持つ人が多い(遺伝的要因)
- ビタミンやミネラルなどの栄養不足

治療法
生活習慣の改善やホルモン剤、抗うつ薬、抗利尿薬などを用いて症状の緩和を図ります。
月経移動

月経移動とは?
月経移動とは、月経周期を意図的に調整することをいいます。
特定のイベントや旅行、スポーツなどの予定に合わせて月経をずらすことができます。
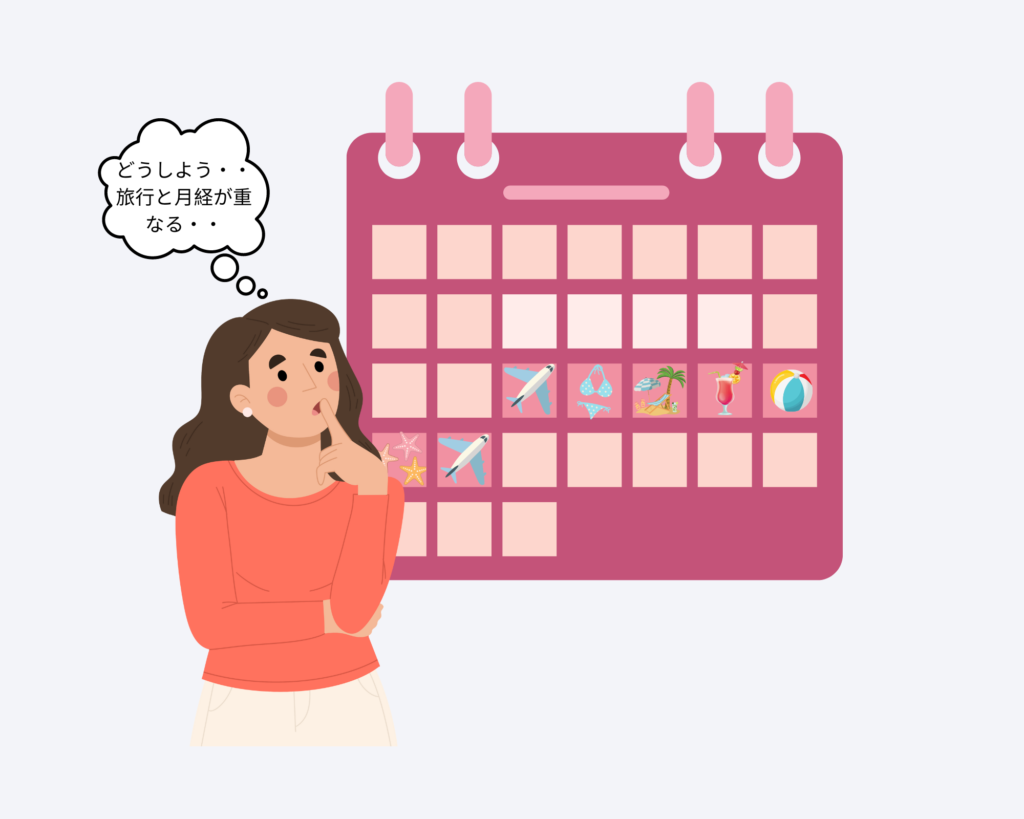

治療法
ホルモン剤を使用し月経を早める、または遅らせます。ご自身の健康状態や今後の予定を考慮し、医師と相談の上月経を移動させます。月経移動は自費診療となります。

料金
自費診療になります。
ピル(経口避妊薬)処方

ピル(経口避妊薬)とは?
ピル(経口避妊薬)とは、妊娠を防ぐために口から摂取するホルモン剤です。主にエストロゲンとプロゲステロンという2種類のホルモンが含まれており、以下のような働きがあります:
排卵の抑制
卵巣からの卵子の排卵を防ぎ、妊娠を防ぎます。
子宮内膜の変化
子宮内膜を薄くすることで、受精卵が着床しにくくします。
粘液の変化
子宮頸部の粘液を変化させ、精子が子宮内に入りにくくします。


他の効果
ピル(経口避妊薬)には、避妊以外にもさまざまな効果があります。
- 生理周期を整え、月経不順を改善します。
- 月経に伴う痛み(月経困難症)を軽減します。
- PMS(月経前症候群)の症状を緩和します。
- ホルモンバランスの調整によりニキビが改善されることがあります。
- 卵巣癌や子宮内膜癌のリスクを低下させる可能性があります。
- 一定のホルモン補充により骨密度が保たれます。
これらの効果は各個人によって異なるため、使用を検討する際は医師と相談し、自分に合った方法を見つけることが重要です。

副作用
ピル(経口避妊薬)を初めて服用する際には、以下のような副作用があることがあります:
- 吐き気
- 頭痛
- 胸の張り
- 気分の変動
- 体重の変化
- 不正出血
- むくみ
- 視覚障害
- 血栓症
これらの副作用はすべての人に現れるわけではなく、多くの場合無症状から軽度であることが多いです。重い副作用や持続的な症状が現れた場合は、直ちに医師にご相談ください。

ピルを服用できない人
✘ 35歳以上で、1日に15本以上煙草を吸っているかた
✘ 血栓症の既往があるかた
✘ 心血管疾患や高血圧があるかた
✘ 重度の糖尿病や肝疾患があるかた
✘ 乳がんや子宮がんなどの既往があるかた
✘ 妊娠中または授乳中のかた

料金
| 診療内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 自費ピル初診料 | 3,300円 |
| 自費ピル再診料(※処方のみの場合も医師の問診があります。) | 0円 |
| 自費低用量ピル ・ファボワール28(マーベロン28) ・ラベルフィーユ28(アンジュ28、トリキュラー28) | 1シート 各2,500円 |
| ピル継続処方時の血液検査 | お問い合わせください。 |
| アフターピル(自費、診察料込み) | 9,000円 |
更年期障害

症状
ほてり、のぼせ、突然の熱感や発汗 (ホットフラッシュ)、発汗、めまい、動悸、頭痛、肩こり、関節の痛み、冷え、疲れやすい、不眠、イライラ、不安、気分が落ち込む、意欲が低下するなどの多彩な症状がみられます。
これらの多彩な症状の陰に、他の深刻な病気がないかを確認しておくことも大切です。そのため産婦人科だけではなく、内科や整形外科、耳鼻科、心療内科、精神科への受診をお勧めすることがあります。


原因
更年期障害の主な原因は、女性ホルモン(エストロゲン)が低下していくことです。さらに、加齢によるからだの変化や、精神的・心理的な要因、家庭や職場などの社会的要因などが複合して、更年期障害を発症すると考えられています。

治療法
更年期障害の治療では、まず問診を行い、患者さんの訴えをお聞きします。次に、生活習慣の改善(食事や運動、睡眠時間の確保など)や心理療法を試みます。それでも症状が改善しない場合は、薬物療法を行います。更年期障害の薬物療法には、ホルモン補充療法 (HRT)、 漢方薬、向精神薬があります。
更年期障害の治療法は、個々の症状やライフスタイルによって異なります。医師と相談し、自分に合った治療法を選ぶことが大切です。
外陰部のかゆみ、おりものの異常、性感染症

症状
外陰部やおりものに異常が見られた場合、以下のような疾患の可能性があります。
おりものの異常
カンジダ膣炎、トリコモナス感染症、クラミジア感染、淋病、細菌性膣症など
かゆみ
カンジダ膣炎、トリコモナス感染症、性器ヘルペス、細菌性膣症
水泡
性器ヘルペス
潰瘍
梅毒
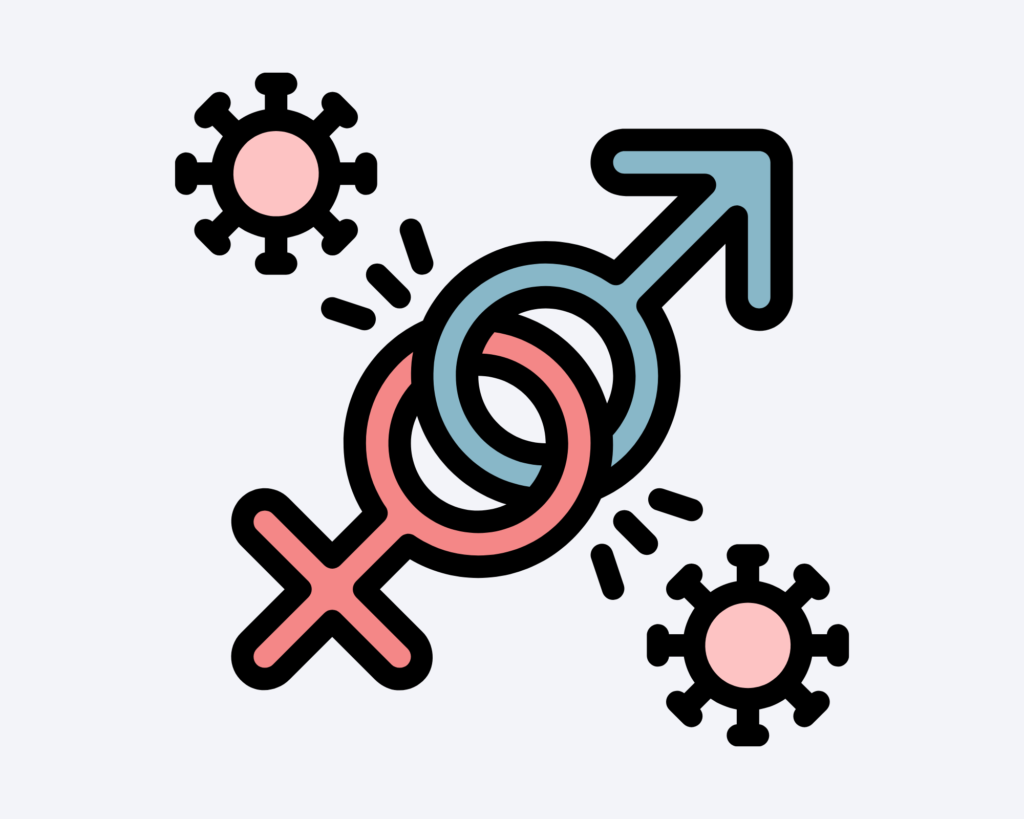
クラミジア感染症
クラミジア・トラコマティスという細菌が原因で起こる性感染症(STD)の一つです。クラミジアは、性行為を通じて主に感染します。女性、男性ともに感染する可能性がありますが、女性は無症状であることも多いため、感染に気づきにくいことがあります。
日本で最も多く報告されている性感染症です。特に若年層に多くみられます。

症状
無症状であることも多いため、感染に気付きくいことがあります。起こり得る症状としては膣分泌物の異常 (量や性状の変化)、排尿時の痛みや違和感、性交時痛などがあり、感染が進行すると下腹部や骨盤部の痛みや発熱などが現れることがあります。

感染経路
主に性行為(膣、肛門、口腔)によって感染します。母子感染することもあります。

診断方法
膣分泌物の検査や尿検査を行います。

原因
クラミジアという細菌の感染。

潜伏時間
感染後1~2週間程度。この期間中は無症状なことが多く、感染者が他者に感染を広げる可能性があります。クラミジアは無症状で進行することが多いため、感染しても気づかないことがよくあります。

治療法
抗生物質によって治療します。
梅毒
梅毒の感染者数は近年急増しており、特に若年層の感染者が増加しています。性感染症全体の中での梅毒の割合も増加傾向です。

症状
初期には無痛性のしこりができ数週間内に自然に消失することがあります。その後、全身に発疹が出現したり、発熱、咽頭痛、筋肉痛などの症状が現れます。その後自然に症状が治まり、長い潜伏期を経て10~30年後に晩期梅毒 (神経梅毒や心血管梅毒) に至ることがあります。

感染経路
主に性行為を通じて感染します。また、妊婦から赤ちゃんに感染することもあります (母子感染) 。

診断方法
視触診と血液検査を行います。

原因
Treponema pallidumという細菌の感染によって引き起こされます。

潜伏時間
感染後、約3週間程度。

治療法
抗生物質を投与します。
淋病
梅毒と同様に増加傾向にあり、Neisseria gonorrhoeaeという細菌によって引き起こされる性感染症(STD)の一つです。淋病は、主に性行為を通じて感染し、放置するとさまざまな合併症を引き起こすことがあります。治療は抗生物質の投与が行われ、早期に治療を受ければ治癒可能です。

症状
無症状のこともあり感染に気づかないこともあります。症状としては、膣分泌物の増加、排尿時痛や違和感、性交時痛、下腹部や骨盤内の痛み、進行すると骨盤内炎症疾患 (PID) に発展することがあります。また、喉の痛み、発熱、腫れ、直腸のかゆみや痛み、排便時痛、 目の結膜炎が発症することがあります。

感染経路
主に膣、肛門、口を介して感染する。また、母子感染することもあります。
主に膣、肛門、口を介した性交渉(膣性交、肛門性交、口腔性交)を通じて感染します。また、感染者の体液(精液や膣分泌物など)と接触することで感染が起こります。
感染部位:淋病は、性器に加えて、喉、直腸、目などさまざまな部位に感染することがあります。

診断方法
尿検査や分泌物の検査を行います。

原因
Neisseria gonorrhoeaeという細菌への感染です。

潜伏時間
2日~1週間程度。

治療法
抗生物質の投与を行います。
カンジダ膣炎

症状
膣や外陰部 (膣の外側) のかゆみ、灼熱感、カッテージチーズのような白いおりものの増加など。

感染経路
カンジダという真菌によって引き起こされる腟の感染症です。カンジダは通常、膣内や腸内に常在している微生物の一種であり、疲労や抗生物質の使用などによる免疫力の低下によって膣内の常在菌のバランスが乱れたことによりカンジダ菌が異常に増殖し、症状を引き起こします。

診断方法
問診、内診 (視診)、培養検査。

原因
主にCandida albicans という種類のカンジダ菌によって引き起こされますが、他の種類のカンジダ菌でも発症することがあります。

潜伏時間
数日〜数週間程度。カンジダ菌は体内に常在する菌であるため、特定の「潜伏期間」という概念は適用されません。

治療法
抗真菌薬、生活習慣の改善。
性器ヘルペス
ヘルペスウイルス(Herpes Simplex Virus, HSV)によって引き起こされる性感染症(STD)の一種です。性器や周辺部位に水疱が出現します。性器ヘルペスは感染力が強く、治療を受けてもウイルスが体内に残り続けるため、再発の可能性があります。

症状
性器や周辺に痛みを伴うみずぶくれや潰瘍が出現します。

感染経路
性器ヘルペスは、感染者との直接的な接触(性行為)を通じて感染します。特に、症状がある時期(水疱やかさぶたが存在している間)に感染しやすいですが、無症状の時期でもウイルスが他者に伝染することがあります。

診断方法
問診、視診、ウイルス検査。

原因
ヘルペスウイルス (Herpes Simplex Virus : HSV)への感染。HSV-1とHSV-2によって引き起こされます。

潜伏時間
通常、2日~2週間程度。

治療法
抗ウイルス薬、鎮痛剤などを用いる。ヘルペスウイルスは治療しても完全には排除できませんが、再発を予防したり、症状を和らげたりすることは可能です。
トリコモナス感染症
Trichomonas vaginalisという原虫が原因で引き起こされる性感染症です。主に女性の膣や男性の尿道に感染しますが、症状が出ない場合もあります。

症状
黄緑色や灰色などの泡立つ、悪臭のあるおりものが特徴的です。また、膣や陰部にかゆみや痛みを呈することがあります。

感染経路
主に性行為を通じて感染しますが、感染者の物品 (タオルなど) を介しても感染することがあります。

診断方法
顕微鏡検査、培養検査。

原因
Trichomonas vaginalisという原虫の感染。

潜伏時間
5日〜28日程度。

治療法
抗原虫薬を投与します。
HIV / AIDS
HIV(ヒト免疫不全ウイルス)感染によるウイルス感染症です。HIVは免疫系の細胞を攻撃し、最終的にAIDS (後天性免疫不全症候群) に進行する可能性があります。HIVに感染しているかたでも適切な治療を受ければ、AIDSの発症を防ぐことができます。

症状
感染初期(急性HIV感染症)では、感染後2〜4週間程度で、風邪やインフルエンザに似た症状が現れることがあります。これを「急性レトロウイルス症候群(ARS)」または「初期HIV症状」と呼びます。
- 感染初期:無症状。
- 急性期(2~4週間程度):風邪やインフルエンザに似た症状(発熱、喉の痛み、倦怠感、リンパ節の腫れなど)。
- 無症状期(数年~10数年程度):免疫系を徐々に弱めていきます。この無症状の期間を臨床潜伏期と呼ばれ数年続くこともあり、この間にHIVウイルスは体内で増殖し続けます。
- AIDS発症:AIDSに進展すると、免疫力が非常に低下し、さまざまな病気にかかりやすくなります。

感染経路
性行為、血液(注射針の使いまわしや血液製剤の使用)、母子感染(妊娠中、出産時、授乳を介して)など。

診断方法
血液検査。

原因
ヒト免疫不全ウイルス (HIV) による感染。

潜伏時間
数週間〜数ヶ月程度。感染後、1〜2ヶ月程度で初期症状が現れることが多いです。

治療法
抗HIV薬(抗レトロウイルス薬)があり、これによりHIVの増殖を抑え、免疫力を維持することが可能です。
肝炎ウイルス感染(B型)
肝炎は、肝臓に炎症を引き起こす疾患で、さまざまな原因によって発症します。肝炎には急性と慢性があり、症状の現れ方や進行の速さは原因によって異なります。最も一般的な原因としてはウイルス感染がありますが、アルコールや薬物、自己免疫反応なども原因となることがあります。肝炎ウィルスにはA型、B型、C型、D型、E型とあります。中でも、特にB型肝炎は性感染症として広がることがあります。

症状
急性および慢性肝炎。慢性の場合は、肝硬変や肝癌のリスクが高まります。

感染経路
血液感染、性行為、母子感染。

診断方法
血液検査。

原因
肝炎ウイルスによる感染。

潜伏時間
約1〜6ヶ月程度。多くの場合、感染後約2〜3ヶ月で症状が現れます。

治療法
ウイルスの種類によって異なりますが、抗ウイルス薬の利用が有効です。また、B型肝炎ワクチンの予防接種や感染対策(コンドーム使用、針の使い回しを避ける)により感染を防ぐことができます。